「題名が思いつかない…」「○○を読んで、じゃダメかな…」
夏休みの宿題で読書感想文を書いている時、一番最初につまずくのが題名(タイトル)ですよね。本は読み終えた、感想も何となくある、でも題名が決まらない。私も学生時代、机に向かって頭を抱えていた記憶があります。
娘が小学生になって読書感想文の宿題を持って帰ってきた時、「お母さん、題名ってどう書けばいいの?」と聞かれて、「そういえば私も困ったなぁ」と懐かしく思い出しました。
でも大丈夫!題名づくりには実はコツがあるんです。ちょっとしたテクニックを使うだけで、「○○を読んで」という平凡な題名が、先生も「おっ!」と目を引く魅力的なタイトルに変身します。
この記事では、読書感想文の題名の書き方について、実際に使える例文を30個以上ご紹介しながら、具体的なテクニックをお伝えします。小学生から高校生まで、学年に応じた題名の付け方も解説しますので、きっとあなたにぴったりの方法が見つかるはずです。
題名で悩んでいる時間はもったいない!さっそく魅力的な題名を作って、読書感想文を完成させましょう。
「読みたい」と思わせるタイトルを考えよう!|題名の役割と重要性
なぜ題名が大切なのか
読書感想文の題名って、実はすごく大切なんです。なぜかというと、題名は読書感想文の「顔」だから。
先生が30人分、40人分の読書感想文を読む場面を想像してみてください。全員が「○○を読んで」という題名だったら…正直、読む前から「またか」という気持ちになってしまいますよね。
でも、その中に「僕が父になった日-『星の王子さま』との出会い」なんていう題名があったら?きっと「どんな内容だろう?」と興味を持って読み始めてくれるはずです。
私の娘の担任の先生も、「題名で工夫している読書感想文は、内容も期待できることが多いんです」とおっしゃっていました。題名に力を入れることで、読書感想文全体の印象がグッと良くなるんですね。
良い題名の3つの条件
良い読書感想文の題名には、次の3つの条件があります:
1. 内容が想像できる
題名を見ただけで、何について書いているのか大まかに分かることが大切です。でも、全部を明かしてしまうのではなく、少し謎を残すくらいがちょうどいいんです。
2. 個性が感じられる
あなたらしさが感じられる題名は、読む人の心に響きます。同じ本を読んでも、感じ方は人それぞれ。その違いを題名に表現できれば最高です。
3. 読みたくなる魅力がある
「続きが気になる」「どういうことだろう?」と思わせる題名は、読書感想文の価値を高めます。
先生が評価するポイント
実際に先生方にお話を聞いてみると、題名で評価するポイントがいくつかあることが分かりました:
- 本の内容と感想文の内容がリンクしているか
- 子どもの成長や気づきが感じられるか
- 創意工夫が見られるか
- 読書を通じて何を学んだかが伝わるか
つまり、ただ目立てばいいというわけではなく、読書感想文の中身をしっかり表現した題名が評価されるんです。
タイトル作りの3つのアイデア|「○○を読んで」では味気ない!
定番タイトルから脱却する方法
「『走れメロス』を読んで」「『注文の多い料理店』を読んで」…確かにシンプルで分かりやすいですが、ちょっと味気ないですよね。
私が娘に教えた方法は、「本のタイトル+自分の感想キーワード」の組み合わせです。例えば:
Before: 「走れメロス」を読んで
After: 友情の重さを知った日-「走れメロス」から学んだこと
このように、ただの書名紹介ではなく、自分が何を感じたかを加えるだけで、グッと魅力的になります。
感情や体験を織り交ぜる
読書感想文の題名に、自分の感情や体験を入れると、オリジナリティが出ます:
感情を入れた例:
- 涙が止まらなかった理由-「かわいそうなぞう」との出会い
- 怒りから理解へ-「こころ」の先生を見つめ直して
- 笑顔になれる魔法-「ぐりとぐら」が教えてくれたこと
体験を入れた例:
- 部活で学んだことと重なった-「バッテリー」を読んで
- 祖母の話を思い出しながら-「おじいさんの時計」
- 転校生だった私が共感した-「窓ぎわのトットちゃん」
問いかけ型タイトルの効果
読む人に問いかける形の題名も効果的です:
- なぜメロスは走り続けたのか?-友情について考える
- お金で買えない物って何だろう?-「星の王子さま」からの問い
- 本当の勇気とは?-「モチモチの木」が教えてくれた答え
このような問いかけ型の題名は、読む人も一緒に考えたくなる効果があります。先生も「どんな答えを出したのかな?」と興味を持って読み進めてくれるはずです。
読書感想文の題名の書き方テクニック1:題名に客観的な事実を表現
客観的事実を使うメリット
読書感想文の題名に客観的な事実を入れると、説得力が増します。「すごい」「感動した」という主観的な言葉より、具体的な事実の方が読む人の興味を引くことがあるんです。
例えば、「ハリー・ポッター」の読書感想文なら:
主観的: すごく面白かったハリー・ポッター
客観的: 7巻4000ページを読破して分かったこと-ハリー・ポッターの真実
客観的な事実(7巻、4000ページ)を入れることで、「それだけ読んだなら、きっと深い感想があるはず」と期待させることができます。
実例で学ぶ客観的表現
実際の本を例に、客観的な事実を使った題名を作ってみましょう:
「走れメロス」の場合:
- 10キロを走り抜いた男の物語-「走れメロス」に見る友情
- たった3日間の約束が生んだ奇跡-「走れメロス」
- 王様を変えた二人の青年-「走れメロス」から学ぶ信頼
「銀河鉄道の夜」の場合:
- 一晩の旅が永遠になった理由-「銀河鉄道の夜」の謎
- カムパネルラが消えた本当の意味-「銀河鉄道の夜」を読み解く
- 宮沢賢治が37年の人生で伝えたかったこと
データや数字を効果的に使う
本に関連するデータや数字を題名に使うのも効果的です:
- 100万人が涙した理由-「君の名は。」小説版を読んで
- 50年読み継がれる意味-「ぐりとぐら」の魅力
- 3分で読める物語に込められた深い意味-「蜘蛛の糸」
ただし、数字を使う時は正確さが大切です。適当な数字を入れてしまうと、かえって信頼性を失ってしまうので注意しましょう。
読書感想文の題名の書き方テクニック2:題名に具体的な数字を入れる
数字が持つインパクト
題名に具体的な数字を入れると、読む人の注意を引きやすくなります。私も実際に娘の読書感想文を手伝った時、数字を入れただけで題名がグッと締まったのを覚えています。
数字なし: 何度も読み返した本
数字あり: 5回読んで初めて気づいた真実-「注文の多い料理店」の秘密
数字があることで、具体性と説得力が増すんです。
効果的な数字の使い方
数字を使った題名の例をいくつかご紹介します:
回数を使った例:
- 3度目の読書で見えてきたもの-「羅生門」の深層
- 10回音読して分かった言葉の美しさ-「雨ニモマケズ」
時間を使った例:
- 一晩で読み切れなかった理由-400ページの「ハリー・ポッター」
- 30分で人生が変わった-「チーズはどこへ消えた?」との出会い
年齢や学年を使った例:
- 14歳の私が共感した主人公-「西の魔女が死んだ」
- 小学6年生最後の夏に読んで良かった本
数字を使う際の注意点
数字を使う時は、以下の点に注意しましょう:
- 正確な数字を使う:適当な数字は逆効果です
- 意味のある数字を選ぶ:ただ数字を入れればいいわけではありません
- 大げさにしない:「1000回感動した」のような誇張は避けましょう
娘の担任の先生も「数字を使った題名は印象に残りやすいけど、中身と関係ない数字だと違和感があります」とおっしゃっていました。
読書感想文の題名の書き方テクニック3:題名に倒置や省略など表現技法を使う
倒置法で印象的な題名を作る
国語の授業で習った「倒置法」を題名に使うと、印象的なタイトルになります。普通の語順を入れ替えることで、読む人の注意を引くんです。
通常の語順: 友達の大切さを「走れメロス」で学んだ
倒置法: 学んだのは友達の大切さ-「走れメロス」を読んで
通常の語順: 「星の王子さま」で大人の心を思い出した
倒置法: 忘れていた、大人になって-「星の王子さま」からのメッセージ
省略法でリズム感を出す
あえて言葉を省略することで、リズム感のある題名が作れます:
省略前: 私は「赤毛のアン」を読んで前向きになることができた
省略後: 前向きになれた。「赤毛のアン」のおかげで
省略前: 「モチモチの木」の豆太が勇気を出した場面に感動した
省略後: 勇気、そして一歩-「モチモチの木」豆太の成長
その他の表現技法
他にも使える表現技法があります:
対比法:
- 弱さと強さ-「走れメロス」に見る人間の二面性
- 子どもの純粋さ、大人の複雑さ-「星の王子さま」
擬人法:
- 本が私に語りかけてきた-「君たちはどう生きるか」
- 物語が教えてくれた大切なこと-「銀河鉄道の夜」
反復法:
- 読んで、考えて、また読んで-「こころ」との対話
- 一歩、また一歩-「アルジャーノンに花束を」と共に歩んだ日々
これらの技法を使うことで、普通の題名が文学的で魅力的なものに変身します。
題名でつまずくのは当たり前|読書感想文の最初の関門
みんな題名で悩んでいる
「題名が決まらない…」と悩んでいるあなた、安心してください。みんな同じです!
私が子どもの頃もそうでしたし、今の娘もそう、娘の友達もみんな題名で悩んでいます。学校の先生に聞いてみたら、「題名で悩まない子の方が珍しいですよ」と笑っていました。
なぜ題名で悩むかというと、読書感想文全体を一言で表現しなければならないから。800字、1200字で書いた内容を、たった20文字程度にまとめるのは、大人でも難しいことなんです。
題名は最後に決めてもOK
実は、題名を最初に決める必要はないんです。むしろ、感想文を書き終えてから題名を考える方が、良いタイトルが浮かびやすいんです。
私が娘に教えた方法:
- まず仮の題名をつける(「○○を読んで」でOK)
- 感想文を最後まで書く
- 書いた内容を読み返す
- 一番伝えたかったことを見つける
- それを題名に反映させる
この方法なら、内容とぴったり合った題名が作れます。
題名づくりの心構え
題名づくりで大切な心構えをお伝えします:
完璧を求めない
最高の題名を作ろうと思うと、かえって手が止まってしまいます。まずは「これでいいかな」というレベルで大丈夫。
他人と比べない
友達がすごい題名を思いついたからといって、焦る必要はありません。あなたにはあなたの感じ方があるはずです。
楽しむ気持ちを忘れない
題名づくりは、実はクリエイティブで楽しい作業。「どんな題名にしようかな〜」とワクワクしながら考えてみてください。
読書感想文の題名づくりに役立つ5つのアイデア
アイデア1:キーワードマッピング
本を読んで感じたことを、思いつくままに書き出してみましょう。私はこれを「キーワードマッピング」と呼んでいます。
例えば「桃太郎」を読んだ場合:
- 勇気
- 仲間
- 鬼退治
- きびだんご
- おじいさんとおばあさん
- 正義
- 冒険
これらのキーワードを組み合わせて題名を作ります:
- 「きびだんごが繋いだ仲間の輪-桃太郎の真の強さ」
- 「一人では成し遂げられなかった鬼退治-仲間の大切さ」
アイデア2:感情の変化を追う
本を読む前と読んだ後の、自分の感情の変化を題名にする方法です:
パターン例:
- 「嫌い」から「理解」へ-「こころ」の先生を見つめ直して
- 「退屈」が「夢中」に変わった瞬間-「ハリー・ポッター」の魔法
- 悲しみを乗り越えて-「かわいそうなぞう」が教えてくれた平和
アイデア3:印象的な一文を活用
本の中で特に印象に残った一文を、題名に活用する方法です:
- 「僕は、きっと王様になれる」-星の王子さまが信じた未来
- 「また明日」という約束-「君の膵臓をたべたい」で知った日常の尊さ
- 「ありがとう」の一言が持つ力-「西の魔女が死んだ」より
アイデア4:比喩を使う
本の内容や感想を、何か別のものに例える方法です:
- 人生という名の列車の旅-「銀河鉄道の夜」を読んで
- 心の扉を開く鍵-「秘密の花園」が教えてくれたこと
- 友情という名の宝物-「宝島」で見つけた本当の宝
アイデア5:時系列で表現
過去・現在・未来の視点を入れる方法です:
- 昨日までの私、今日からの私-「君たちはどう生きるか」を境に
- 10歳で読んだ意味-「エルマーのぼうけん」と成長
- 未来の自分に伝えたいこと-「アンネの日記」からの学び
読書感想文の書き方!題名・書き出し~結論まで構成のコツ
全体構成を考えてから題名を決める
読書感想文は、題名だけでなく全体の構成が大切です。私が娘に教えた構成は:
- 題名(15〜20文字程度)
- 書き出し(つかみ・100〜150字)
- あらすじ(簡潔に・150〜200字)
- 感想・考察(メイン・400〜600字)
- 結論(まとめ・100〜150字)
この構成を意識すると、題名も自然に決まってきます。
題名と書き出しの連動
題名と書き出しは連動させると効果的です:
題名: なぜメロスは走り続けたのか
書き出し: 「もし自分がメロスだったら、本当に戻って来られただろうか。」この疑問が、私の頭から離れませんでした。
題名: 14歳の私が泣いた理由
書き出し: 本を読んで泣いたのは、生まれて初めてでした。「西の魔女が死んだ」の最後のページを閉じた時、私の頬には涙が伝っていました。
結論から逆算して題名を作る
実は、結論(自分が一番伝えたいこと)を先に決めてから、題名を考える方法もおすすめです。
例えば、結論が「友達の大切さを学んだ」なら:
- 題名:一人では生きていけない-「走れメロス」が教えてくれた友情の価値
- 題名:信じることの強さ-メロスとセリヌンティウスの絆
結論がはっきりしていると、題名も自然に浮かんできます。
まずはあらすじを書き出し、読書感想文の構成の下書きを
あらすじを整理する重要性
題名を考える前に、まず本のあらすじを整理することが大切です。なぜなら、あらすじを整理することで、自分が何に感動したのか、何を伝えたいのかが明確になるからです。
私が実践している方法:
- 起承転結で4つに分ける
- それぞれを1〜2文でまとめる
- 特に印象に残った場面に印をつける
- その場面から題名のヒントを探す
下書きから題名を導き出す
実際に「走れメロス」で実践してみましょう:
起: メロスが王様の怒りを買い、処刑されそうになる
承: 妹の結婚式のため3日間の猶予をもらう(★印象的)
転: 様々な困難に遭いながらも必死に戻ろうとする(★印象的)
結: 約束を守り、王様の心を変える
印象に残った部分から題名を考えると:
- 「3日間の約束が生んだ奇跡」
- 「走り続けた理由-信頼という名の鎖」
感情の動きをメモする
あらすじを書きながら、その時々の自分の感情もメモしておきましょう:
- 序盤:「王様ひどい!」(怒り)
- 中盤:「メロス、本当に戻るの?」(不安)
- 終盤:「やった!信じて良かった」(感動)
この感情の変化を題名に活かすこともできます:
- 「怒りから感動へ-走れメロスが教えてくれた信頼の力」
差をつける!読書感想文のタイトル付けテク
学年別の題名レベル
学年によって、求められる題名のレベルも変わってきます:
小学校低学年(1〜3年生):
- シンプルで分かりやすい題名
- 例:「ぐりとぐらとぼくの大すきなカステラ」
- 例:「うさぎとかめから学んだこと」
小学校高学年(4〜6年生):
- 少し工夫を加えた題名
- 例:「なぜ豆太は木に登れたのか-勇気の正体」
- 例:「6年生の私が見つけた宝物-『トム・ソーヤの冒険』」
中学生:
- 抽象的な概念も使える題名
- 例:「正義とは何か-『羅生門』が投げかける問い」
- 例:「14歳の葛藤と共鳴-『西の魔女が死んだ』を読んで」
高校生:
- より深い考察を示す題名
- 例:「近代的自我の芽生え-『こころ』における個人と社会」
- 例:「不条理の中の希望-カフカ『変身』から見る現代社会」
コンクール入賞作品の題名分析
実際のコンクール入賞作品の題名には、共通点があります:
具体性と抽象性のバランス:
- 「おばあちゃんの味噌汁と私の決意」(具体+抽象)
- 「1945年の夏を生きる-『はだしのゲン』との対話」(具体的な年+抽象的な対話)
個人的な体験との結びつき:
- 「転校生の私だから分かったこと」
- 「父との約束を思い出した日」
問題提起型:
- 「AIに心は宿るのか-『アンドロイドは電気羊の夢を見るか』」
- 「本当の優しさとは何か」
オリジナリティを出すコツ
他の人と差をつけるためのコツ:
- 自分にしか書けない視点を入れる
- 部活動との関連
- 家族との思い出
- 最近のニュースとの関連
- 意外な組み合わせ
- 古典作品×現代の問題
- 童話×哲学的な問い
- 冒険小説×日常生活
- 読後の行動を入れる
- 「読んでから始めた新習慣」
- 「本棚を整理した理由」
- 「友達に薦めたくなった瞬間」
書き出しでスパイスを出し、読書感想文を展開させていく
題名と書き出しの黄金コンビ
題名で興味を引いたら、書き出しでさらに読み手を引き込みます。この「題名→書き出し」の流れが、読書感想文の成功の鍵なんです。
パターン1:題名の謎を書き出しで説明
題名:「3秒で世界が変わった瞬間」
書き出し:「主人公が振り返った、たった3秒。その瞬間、私の本に対する見方が180度変わりました。」
パターン2:題名と対比させる書き出し
題名:「勇気ある一歩」
書き出し:「私は臆病者です。虫も苦手だし、暗い場所も怖い。でも、この本を読んで…」
パターン3:題名を具体的にする書き出し
題名:「本当の友達」
書き出し:「クラスに友達は30人いる。でも、本当の友達は何人いるだろう?」
インパクトある書き出し例
実際に使える書き出しの例をご紹介します:
質問から始める:
- 「もし、明日地球が滅亡するとしたら、あなたは何をしますか?」
- 「お金で買えないものって、本当にあるのでしょうか?」
衝撃的な一文から:
- 「私は、この本を読んで人生観が変わりました。大げさではありません。」
- 「正直に言います。最初、この本を読みたくありませんでした。」
場面描写から:
- 「夏休み最後の日、エアコンの効いた部屋で、私は泣いていました。」
- 「図書館の片隅で、ほこりをかぶったその本は、私を待っていたのかもしれません。」
書き出しから展開へのつなげ方
書き出しで読み手の心をつかんだら、スムーズに本文へつなげます:
- 書き出し:問題提起やエピソード
- つなぎ:「この本を読んで」「そんな時に出会ったのが」
- 展開:あらすじや具体的な感想へ
この流れを意識すると、自然な読書感想文が書けます。
読書感想文の完成に向けてブラッシュアップ!
題名の最終チェックポイント
読書感想文が書き終わったら、題名を最終チェックしましょう。私がいつも娘と一緒に確認するポイントは:
チェックリスト:
□ 内容と題名が合っているか
□ 長すぎないか(20文字以内が理想)
□ 難しすぎる言葉を使っていないか
□ 本のタイトルが分かるようになっているか
□ 自分らしさが出ているか
一つでも「いいえ」があったら、もう一度考え直してみましょう。
声に出して確認する
題名は声に出して読んでみることが大切です。声に出すと:
- リズムが良いか分かる
- 言いにくい部分が見つかる
- 印象の強さが確認できる
娘も「声に出したら、なんか違う感じがした」と言って、題名を修正したことがあります。
家族や友達に意見をもらう
恥ずかしいかもしれませんが、家族や友達に題名を見てもらうのもおすすめです:
「この題名見て、どんな内容か想像できる?」
「読みたくなった?」
「もっと良い題名ある?」
私も娘の読書感想文の題名について、家族会議を開いたことがあります(笑)。みんなでアイデアを出し合うと、思いもよらない良い題名が生まれることがありますよ。
読書感想文の例文を見ながら書き方コツを押さえる
小学生向け題名例文集
実際の本を使った題名の例文をたくさんご紹介します:
「ごんぎつね」の題名例:
- いたずらぎつねの本当の気持ち
- ごんの優しさに気づけなかった兵十と私
- 赤い彼岸花とごんの思い出
- 撃たれても伝えたかったこと-ごんぎつねの願い
- 4年生の私が初めて泣いた物語
「モチモチの木」の題名例:
- 臆病な豆太が見せた本当の勇気
- おじいちゃんのために走った夜
- モチモチの木に灯がともった理由
- 怖がりな私と豆太の共通点
- 一歩踏み出す勇気をくれた物語
「スイミー」の題名例:
- 小さな魚の大きな知恵
- みんなで作った巨大な魚-協力の大切さ
- 黒い魚スイミーが教えてくれたこと
- 一人じゃないって素敵なこと
- 海の中の小さなリーダー
中学生向け題名例文集
「走れメロス」の題名例:
- 人を信じることの重さと美しさ
- 暴君を変えた二人の青年の友情
- なぜメロスは死を覚悟して戻ったのか
- 信頼という見えない絆の強さ
- 現代に生きる私たちへのメッセージ
「坊っちゃん」の題名例:
- 正直者が損をする?-坊っちゃんの生き方
- 明治の教師と令和の中学生
- 赤シャツへの怒りと共感
- 江戸っ子気質が教えてくれる正義
- 不器用でも真っ直ぐに-坊っちゃんから学んだこと
「羅生門」の題名例:
- 生きるための悪は許されるのか
- 下人の選択と現代社会の闇
- 羅生門の上で揺れた正義の天秤
- 極限状態で人は何を選ぶのか
- 善悪の境界線を考える-芥川龍之介の問い
高校生向け題名例文集
「こころ」の題名例:
- エゴイズムと愛の狭間で-先生の苦悩
- 明治の終焉と個人の自我
- なぜ先生は死を選んだのか-近代的自我の限界
- 「私」が継承したものは何か
- 友情と恋愛が生んだ悲劇の構造
「人間失格」の題名例:
- 道化を演じ続けた男の真実
- 「人間失格」は本当に失格なのか
- 太宰治の自己告白と普遍的な孤独
- 恥の多い生涯から見える人間の本質
- 現代にも通じる疎外感との対峙
読書感想文のタイトル|書く場所はどこ?
原稿用紙での題名の書き方
題名を書く場所って、意外と迷いますよね。正しい書き方を確認しましょう:
基本ルール:
- 1行目:空ける
- 2行目:題名を書く(上を2〜3マス空ける)
- 3行目:学校名・学年・氏名(下を1マス空けて書き始める)
- 4行目:空ける
- 5行目:本文開始
題名が長い場合:
題名が1行に収まらない時は、2行目の中央から書き始め、3行目に続きを書きます。その場合、氏名は4行目に書きます。
パソコンで作成する場合
最近はパソコンで読書感想文を作成することも増えています:
Word等での設定:
- フォント:明朝体が一般的
- 題名のサイズ:本文より2〜4ポイント大きく
- 題名の配置:中央揃え
- 本文との間:1行空ける
学校によってルールが異なる場合があるので、必ず確認しましょう。
題名に使える記号と使えない記号
題名に使える記号と使えない記号があります:
使える記号:
- 「」(かぎかっこ):本のタイトルを示す時
- -(ダッシュ):副題をつける時
- ・(中黒):並列を表す時
- ?!:疑問や感嘆を表す時(学校による)
避けた方がいい記号:
- ♪♥などの装飾記号
- 顔文字
- 〜(波線)の多用
- ★☆などの記号(学校による)
娘の学校では「?」「!」は使っても良いけど、装飾的な記号はNGでした。事前に確認しておくと安心です。
まとめ|読書感想文の題名で差をつけよう
ここまで、読書感想文の題名の書き方について詳しくご紹介してきました。
最初は「題名が思いつかない…」と悩んでいたあなたも、今ならきっと素敵な題名が作れるはずです。私の娘も、最初は「○○を読んで」しか思いつかなかったのが、今では「お母さん、こんな題名どう?」と自信を持って見せてくれるようになりました。
題名づくりのポイントをもう一度整理すると:
- 「○○を読んで」から脱却する
- 感情や体験を加える
- 問いかけ形式にする
- 印象的なキーワードを使う
- 3つのテクニックを活用
- 客観的事実を入れる
- 具体的な数字を使う
- 倒置法などの表現技法を使う
- 内容との一致を大切に
- 感想文の中身をしっかり表現
- 大げさすぎない
- 自分らしさを忘れない
- 学年に応じたレベルで
- 小学生:シンプルで分かりやすく
- 中学生:少し抽象的な概念も
- 高校生:深い考察を示す
そして何より大切なのは、楽しんで題名を考えることです。
「どんな題名にしたら先生が驚くかな?」「友達に『すごい!』って言われる題名は?」と、ワクワクしながら考えてみてください。題名づくりは、あなたの創造力を発揮できる素晴らしいチャンスなんです。
読書感想文の題名は、あなたの個性を表現する大切な一文です。今回ご紹介したテクニックや例文を参考にしながら、あなただけの素敵な題名を作ってくださいね。
きっと先生も「おっ!」と目を引く、素晴らしい読書感想文が完成するはずです。頑張ってください!
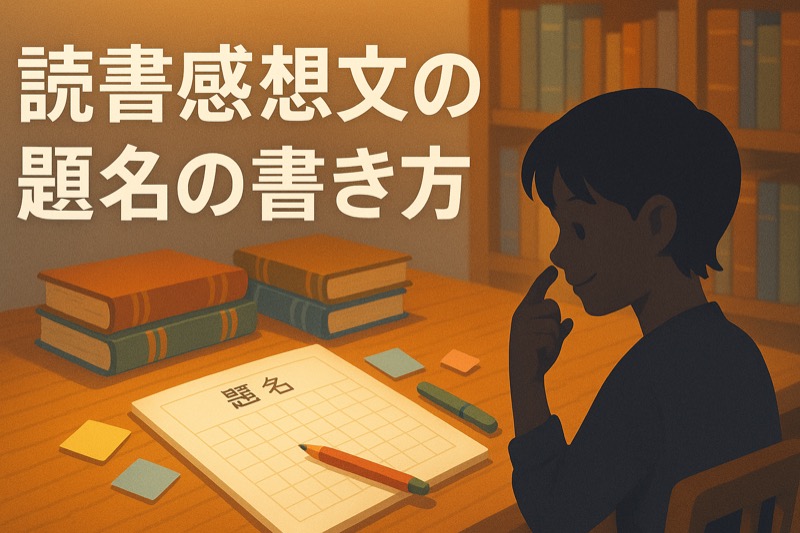
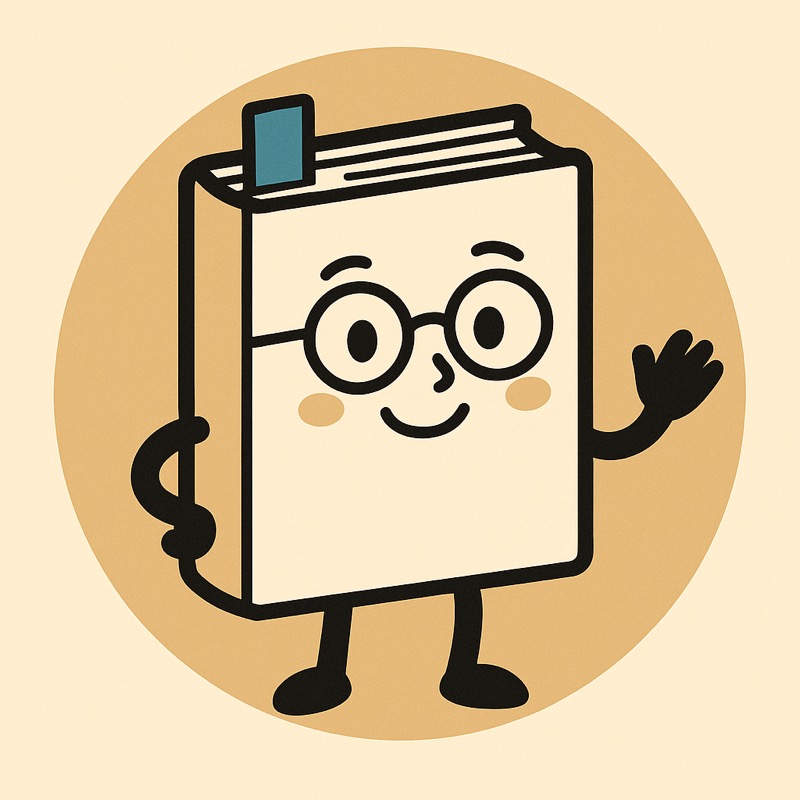
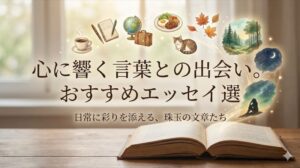


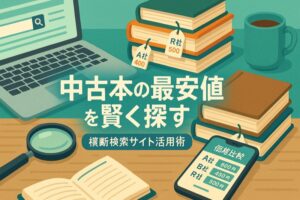


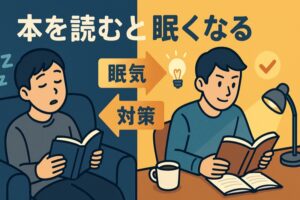

コメント