「本を読むのが遅くて、試験時間が足りない……」
「周りと比べて、自分の読書スピードってどうなんだろう?」
そんな悩みを抱えていませんか?実は、本を読むスピードは、ちょっとしたコツを知っているだけで劇的に速くなるんです。私自身、以前は1ページ読むのに5分もかかっていましたが、今では同じ時間で10ページ読めるようになりました。
この記事では、日本人の平均読書速度から、本を速く読むための具体的な方法、自宅でできるトレーニング法まで、初心者でもすぐに実践できる情報を網羅的にお届けします。
読書スピードが上がれば、学習効率が向上し、試験でも余裕が生まれます。「もっと速く読めるようになりたい」そんなあなたに、今日から使えるテクニックを詳しく解説します。
本を読むスピードの平均はどのくらい?【年代別データ】
「自分の読書スピード、平均と比べてどうなんだろう?」
まずは気になる平均データから見ていきましょう。自分の立ち位置を知ることが、読書スピード向上の第一歩です。
日本人の平均読書速度は分速400〜600文字
日本人の一般的な読書速度は、分速400〜600文字と言われています。
これは、原稿用紙1枚分(400文字)を1分で読めるかどうか、というペースです。1ページ300文字程度の文庫本なら、1ページを約30秒〜45秒で読む計算になります。
ただし、これはあくまで平均値。本の難易度や内容、読む目的によって大きく変わります。小説なら速く読めても、専門書や論文だとペースが落ちるのは当然のことです。
💡 読書速度の目安
- 遅い:分速200〜300文字
- 普通:分速400〜600文字
- 速い:分速800〜1,000文字
- 速読レベル:分速2,000文字以上
小学生の読書スピード:学年別の平均データ
小学生の読書速度は、学年が上がるにつれて段階的に速くなっていきます。
| 学年 | 平均読書速度 | 特徴 |
|---|---|---|
| 小学1〜2年生 | 分速100〜200文字 | 一文字ずつ読む段階 |
| 小学3〜4年生 | 分速200〜300文字 | 単語単位で読めるように |
| 小学5〜6年生 | 分速300〜400文字 | 大人に近づき始める |
小学生のうちは、まだ音読の習慣が残っているため、読書スピードはゆっくりです。これは成長の過程で自然なことなので、焦る必要はありません。
中学生・高校生の読書スピードの目安
中学生・高校生になると、読書速度は大人とほぼ同じレベルに達します。
中学生:分速400〜500文字
音読から黙読へとしっかり切り替わり、文章をかたまりで理解できるようになります。ただし、古文や漢文など慣れない文章では、まだスピードが落ちることも。
高校生:分速500〜600文字
大人の平均的な読書速度とほぼ同じレベル。受験勉強を通じて、大量の文章を読む経験を積むため、この時期に読書速度が大きく伸びる人が多いです。
⚠️ 読書速度が伸び悩む高校生へ
試験勉強で大量の文章を読んでいるのに、読書速度が伸びない場合、「戻り読み」や「音読癖」が原因かもしれません。後ほど詳しく解説します。
大人の読書速度と速読の基準
大人の読書速度は、職業や読書習慣によって大きく変わります。
一般的な大人:分速400〜600文字
新聞や小説を普通に読むペース。日常生活では十分なスピードです。
読書習慣のある人:分速600〜800文字
定期的に本を読む人は、自然と読書速度が速くなります。ビジネス書を月に数冊読むような人は、このレベルに達していることが多いです。
速読トレーニング済み:分速1,000〜3,000文字
速読のトレーニングを受けた人は、分速1,000文字を超えます。プロの速読者になると、分速10,000文字以上読める人もいます。
自分の読書スピードを測定する簡単な方法
自分の読書スピードを知りたいときは、簡単に測定できます。
【測定方法】
- 読みやすい小説や新書を用意する
- タイマーを1分にセットする
- スタートと同時に、普段通りの速さで読み始める
- 1分経ったら止めて、読んだ文字数を数える
文字数は、1行あたりの文字数×読んだ行数で計算できます。文庫本なら1行約40文字、1ページ約15行が目安です。
これを3回ほど繰り返して平均を取ると、より正確な自分の読書速度がわかります。
本を読むスピードが遅い5つの原因と改善ポイント
「自分の読書スピード、平均より遅いかも……」
そう感じた方も大丈夫。読書スピードが遅いのには、必ず原因があります。原因がわかれば、改善策も見えてきます。ここでは、本を読むのが遅い人に共通する5つの原因と、その改善ポイントを解説します。
音読癖が残っている(黙読でも頭の中で音読)
これ、読書スピードが遅い人の最大の原因です。
黙読しているつもりでも、頭の中で「声に出して読んでいる」状態になっていませんか?この「心の中で音読する癖」があると、どうしても読むスピードが遅くなってしまうんです。
なぜなら、音読のスピードは、どんなに速くてもアナウンサー並みの分速300〜350文字が限界だから。黙読なら分速600文字以上出せるのに、音読癖があるとその半分のスピードしか出ません。
【改善ポイント】
意識的に「文字を見る」だけにして、声に出さない練習をします。最初は違和感がありますが、慣れると自然に速く読めるようになります。ガムを噛みながら読むと、音読を防げるという人もいます。
一文字ずつ目で追ってしまう
小学生のときの読み方が抜けていない、というパターンです。
一文字ずつ、カタカタカタと目で追っていくと、当然読むスピードは遅くなります。大人の読書は、単語や文節をかたまりで捉えることが大切なんです。
たとえば、「私は昨日本を読みました」という文章を、「わ・た・し・は・き・の・う・ほ・ん・を」と一文字ずつ読むのではなく、「私は / 昨日 / 本を / 読みました」と意味のかたまりで読む。これだけで、読書速度は2倍以上速くなります。
【改善ポイント】
視野を広げるトレーニングが効果的。3〜5文字をまとめて見る練習をすると、自然とかたまりで読めるようになります。
戻り読みが多すぎる
「あれ、今なんて書いてあった?」と、何度も前に戻って読み直していませんか?
戻り読みは、理解を深めるためには必要なこともありますが、あまりに頻繁だと読書スピードが大幅に落ちてしまいます。研究によると、読書スピードが遅い人は、平均して3行読むごとに1回戻り読みをしているそうです。
戻り読みの原因は、集中力不足や、一度で理解しようとするプレッシャーであることが多いです。
【改善ポイント】
「とりあえず最後まで読む」という意識を持つこと。わからない部分があっても、まず全体を読み終えてから戻る方が、結果的に理解も深まります。指やペンで行をガイドしながら読むと、戻り読みを防げます。
集中力が続かない・すぐに気が散る
スマホが気になる、周りの音が気になる、眠くなる……集中力が続かないと、当然読書スピードは落ちます。
現代人は、スマホやSNSの影響で、集中力の持続時間が短くなっていると言われています。実際、10分も本を読めば、無意識にスマホに手が伸びる、という人も多いのではないでしょうか。
【改善ポイント】
読書環境を整えることが第一。スマホは別の部屋に置く、読書専用の場所を作る、タイマーで区切って集中する(ポモドーロ・テクニック)など、工夫次第で集中力は高められます。
📝 ポモドーロ・テクニックとは?
25分集中して読書→5分休憩、を繰り返す方法。集中力が持続しやすく、読書量も自然と増えます。
本を速く読むための具体的な方法5選
原因がわかったところで、次は具体的な解決策です。
ここでは、本を速く読むための実践的な方法を5つご紹介します。どれも今日から試せる方法なので、ぜひ実践してみてください。
視野を広げて文章を「面」で捉える
速く読むための最も基本的で、最も効果的な方法です。
一文字ずつ「点」で読むのではなく、3〜5文字、さらには一行全体を「面」として捉える。これが速読の基本中の基本です。
最初は難しく感じるかもしれませんが、練習すれば誰でもできるようになります。新聞の見出しを見るとき、一文字ずつ読まずに一瞬で全体を把握できますよね?それと同じ感覚です。
【練習方法】
新聞のコラムを使って練習するのがおすすめ。縦書きの文章を、視線を上から下にまっすぐ動かすだけで読めるよう練習します。最初は内容が頭に入らなくても、繰り返すうちに自然と理解できるようになります。
指やペンでガイドしながら読む
これ、意外とバカにできません。
指やペンで読んでいる行をなぞりながら読むと、目の動きがスムーズになり、戻り読みを防げます。小学生が指差しながら読むのと同じですが、大人がやっても効果抜群です。
ポイントは、指を一定のリズムで動かすこと。徐々にスピードを上げていくと、自然と読むペースも上がります。
✅ 指ガイド読書のメリット
- 戻り読みが減る
- 集中力が高まる
- 読むスピードを自分でコントロールできる
目的を明確にして必要な情報だけを拾う
すべての本を、隅から隅まで精読する必要はありません。
「この本から何を得たいか」という目的を明確にして、必要な情報だけを拾い読みする。これも立派な速読テクニックです。
たとえば、ビジネス書なら目次を見て興味のある章だけを読む、小説なら会話文だけをザッと読んで流れを掴む、といった具合です。本の種類によって読み方を変えることで、効率が大幅にアップします。
予習読みで全体像を先に把握する
本を読む前に、5分だけ「予習」をしてみてください。
具体的には、目次をしっかり読む、各章の冒頭と最後だけを読む、図表だけをザッと見る、といった方法です。全体の構成がわかっていると、読むスピードが格段に上がります。
地図を見てから旅行に出るのと同じで、全体像を把握してから読むと、迷わず進めるんです。
| 読み方 | 向いている本 | 速度 |
|---|---|---|
| 精読 | 文学作品・専門書 | 分速300〜500文字 |
| 通常読み | 小説・一般書 | 分速500〜800文字 |
| 速読 | ビジネス書・雑誌 | 分速1,000文字以上 |
| スキミング(拾い読み) | 情報収集用の本 | 分速2,000文字以上 |
読書スピードを上げる自宅でできるトレーニング法
「理論はわかった。でも、具体的にどう練習すればいいの?」
そんな声が聞こえてきそうです。ここでは、自宅で今日からできる、読書スピード向上のためのトレーニング法をご紹介します。
目の動きを鍛える眼筋トレーニング
読書速度を上げるには、目の動きを速くすることが重要です。
眼筋(目を動かす筋肉)を鍛えることで、目の動きがスムーズになり、文字を追うスピードが上がります。
【簡単眼筋トレーニング】
- 顔を動かさず、目だけで左右を見る(各5秒キープ)×10回
- 顔を動かさず、目だけで上下を見る(各5秒キープ)×10回
- 目だけで8の字を描くように動かす×10回
- 遠くと近くを交互に見る×10回
これを毎日3分やるだけで、目の動きが劇的に速くなります。スマホの見すぎで凝り固まった目の筋肉もほぐれるので、一石二鳥です。
タイマーを使った速読練習
読書速度を上げるには、「時間制限」がとても効果的です。
タイマーを使って、少しずつ読む時間を短くしていく練習をします。
【トレーニング方法】
- 普段通りのペースで1ページ読み、時間を測る
- 次は、その時間の90%で読むことを目標にする
- さらに次は80%、70%……と徐々に速くする
- 理解度が下がらない範囲で、最速タイムを記録する
このトレーニングを1日10分、1週間続けると、読書スピードが確実に上がります。私もこの方法で、1ヶ月で読書速度が1.5倍になりました。
簡単な本から段階的にスピードアップ
いきなり難しい本で速読の練習をしても、挫折するだけです。
まずは読みやすい本、たとえばライトノベルやエッセイ、雑誌記事などで速読の感覚を掴みましょう。慣れてきたら、徐々に難易度を上げていきます。
【おすすめの練習順序】
- 新聞のコラム(短くて読みやすい)
- エッセイ・ブログ記事
- ライトノベル・ミステリー小説
- ビジネス書・実用書
- 専門書・学術書
階段を一段ずつ登るように、無理なくレベルアップしていくことが大切です。
本を速く読めるメリットと学習・仕事への効果
「速く読めるようになって、何かいいことあるの?」
もちろんあります!読書スピードが上がると、人生が変わると言っても過言ではありません。ここでは、本を速く読めることのメリットをご紹介します。
学習効率が劇的に向上する
読書スピードが2倍になれば、同じ時間で2倍の情報を得られます。
受験勉強や資格試験の勉強をしている人にとって、これは圧倒的なアドバンテージ。参考書を2周できるか、1周しかできないかでは、理解度に大きな差が出ます。
実際、難関大学に合格する学生の多くは、読書速度が速いという調査結果もあります。限られた時間で大量の情報を処理する能力が、学習効率を左右するんです。
情報収集のスピードが上がり仕事で差がつく
社会人にとっても、読書スピードは武器になります。
ビジネス書を月に10冊読む人と、1冊しか読まない人では、1年後には圧倒的な知識の差が生まれます。業界の最新情報を素早くキャッチアップできれば、仕事でも一歩先を行けます。
メールや資料を読むスピードも速くなるので、日々の業務効率も上がります。
読書量が増えて知識・教養が深まる
読書スピードが上がれば、当然読書量も増えます。
月に1冊しか読めなかった人が、5冊読めるようになる。1年で60冊。10年で600冊。この差は、人生を大きく変えます。
知識が増えれば視野が広がり、人生の選択肢も増える。読書は、自分への最高の投資なんです。
📖 読書スピードが上がると…
- 試験で時間が余るようになる
- 仕事の資料をサクサク読める
- 読みたかった本をどんどん消化できる
- 知識が増えて会話の引き出しが増える
入試・試験で必要な読書スピードの目安と対策
「試験で時間が足りない……」
これ、受験生や資格試験受験者の最大の悩みですよね。ここでは、各種試験で求められる読書速度と、その対策をご紹介します。
大学入試の現代文で求められる読書速度
大学入学共通テスト(旧センター試験)の現代文では、約80分で約6,000〜7,000文字を読む必要があります。
単純計算すると、分速800〜1,000文字のスピードが必要。しかも、読むだけでなく設問を解く時間も必要なので、実際にはもっと速く読む必要があります。
余裕を持って解答するには、分速1,200文字以上の読書速度が理想的です。
資格試験・公務員試験での読解スピード
行政書士試験や公務員試験など、文章量が多い試験では、読書スピードが合否を分けます。
特に公務員試験の文章理解問題は、時間との戦い。1問あたり3〜4分で解く必要があるため、文章を素早く読んで要点を掴む能力が求められます。
目標は、分速1,000文字以上。これくらいのスピードがあれば、ほとんどの試験で時間に余裕が生まれます。
試験時間内に読み切るための時間配分術
試験では、ただ速く読めばいいわけではありません。戦略的な時間配分が重要です。
【試験での読解テクニック】
- まず設問を読んで、何を問われているか把握する
- 本文は全部読まず、設問に関係する部分を中心に読む
- 選択肢を先に見て、探すべきキーワードを頭に入れる
- 迷った問題は後回しにして、時間配分を守る
速く読むことと、効率よく読むことは違います。試験では、「必要な情報を素早く見つける力」が求められるんです。
本を速く読む際に見落としがちな3つの注意点
「速く読めるようになった!でも、内容が頭に入らない……」
速読には落とし穴もあります。ここでは、本を速く読む際に見落としがちな注意点を3つご紹介します。
スピード重視で理解度が下がる落とし穴
これ、速読初心者が最もやりがちな失敗です。
速く読むことに夢中になって、内容が全く頭に入っていない。これでは本末転倒です。大切なのは、「速く読むこと」ではなく「速く読んで理解すること」。
目安として、理解度は最低でも7割はキープしたいところ。読み終わった後に、「この本は何について書いてあったか」を3行で説明できないようなら、読むスピードを落とすべきです。
すべての本を速読する必要はない
小説を味わって読むのも、大切な読書です。
ビジネス書や情報収集のための本は速読で効率よく、文学作品や哲学書はじっくり精読で。本の種類や目的によって、読み方を変えることが大切です。
すべての本を速読しようとすると、読書の楽しみが失われてしまいます。
疲労がたまると逆効果になる
速読は、思っている以上に脳を使います。
無理に速く読み続けると、集中力が切れて逆に効率が下がります。適度に休憩を取りながら、自分のペースで読むことが大切です。
1時間読んだら10分休憩、くらいのペースがちょうどいいでしょう。
右脳速読トレーニングで読書スピードを劇的に向上させる方法
最後に、最も効果的な速読法の一つ、「右脳速読」についてご紹介します。
右脳速読とは?従来の速読との違い
従来の速読は、左脳を使った「文字を高速で処理する」方法でした。
一方、右脳速読は、文字を「イメージ」として捉える方法。文字を一つひとつ読むのではなく、ページ全体を写真のように脳に取り込むイメージです。
右脳は視覚情報の処理が得意なので、イメージとして捉えることで、左脳だけで読むよりも格段に速く情報を処理できます。
イメージ化トレーニングで理解力を保つ
右脳速読の鍵は、「文字をイメージに変換する」能力です。
たとえば、「青い海」という文字を見たら、実際に青い海の景色を頭の中に思い浮かべる。この習慣をつけることで、読むスピードが上がっても理解度が下がりません。
【イメージ化トレーニング】
簡単な文章(「赤いリンゴ」「大きな犬」など)を読んで、瞬時にイメージを思い浮かべる練習をします。慣れてきたら、文章を長くしていきます。
右脳速読の4つのステップ
右脳速読は、段階的にトレーニングすることで身につけられます。
【ステップ1】視野拡大トレーニング
目の動きを最小限にして、一度に見える範囲を広げる練習。
【ステップ2】イメージ化トレーニング
文字を見た瞬間にイメージを思い浮かべる練習。
【ステップ3】高速読みトレーニング
理解度を気にせず、とにかく高速でページをめくる練習。脳に高速処理の感覚を覚えさせます。
【ステップ4】理解度を保ちながら速読
ステップ1〜3を組み合わせて、理解しながら速く読む練習。
右脳速読は、習得に時間がかかりますが、マスターすれば分速2,000文字以上も夢ではありません。
まとめ
ここまで、本を読むスピードの平均から、速く読むための具体的な方法、トレーニング法まで、幅広くご紹介してきました。
最後にもう一度、大切なポイントをおさらいしましょう。
読書スピードの平均は、分速400〜600文字です。
自分の読書速度を測定して、まずは現在地を知ることが第一歩。平均より遅くても、今日から練習すれば必ず速くなります。
読書スピードが遅い原因は、音読癖・一文字読み・戻り読み・集中力不足です。
原因を特定して、一つずつ改善していきましょう。すべてを一度に直そうとせず、まず一つの癖を直すことに集中するのがコツです。
本を速く読むには、視野を広げる・指でガイドする・目的を明確にするなどの方法が効果的です。
今日から実践できる方法ばかりです。まずは自分に合いそうな方法を一つ選んで、1週間試してみてください。
読書スピードを上げるには、毎日のトレーニングが重要です。
眼筋トレーニング、タイマーを使った練習、簡単な本から段階的にレベルアップ。1日10分の練習で、1ヶ月後には確実に効果が出ます。
速く読めることのメリットは計り知れません。
学習効率が上がり、仕事で差がつき、読書量が増えて人生が豊かになる。読書スピード向上への投資は、必ず大きなリターンとなって返ってきます。
ただし、理解度を犠牲にしないこと。
速く読むことが目的ではなく、速く読んで理解することが目的です。本の種類によって読み方を変え、疲れたら休憩を取る。無理をせず、自分のペースで続けることが何より大切です。
さあ、この記事を参考に、あなたも読書スピードアップにチャレンジしてみてください。1ヶ月後、3ヶ月後の自分が、きっと「やってよかった」と思えるはずです。
本を速く読めるようになれば、世界が広がります。あなたの読書ライフが、より充実したものになることを願っています。
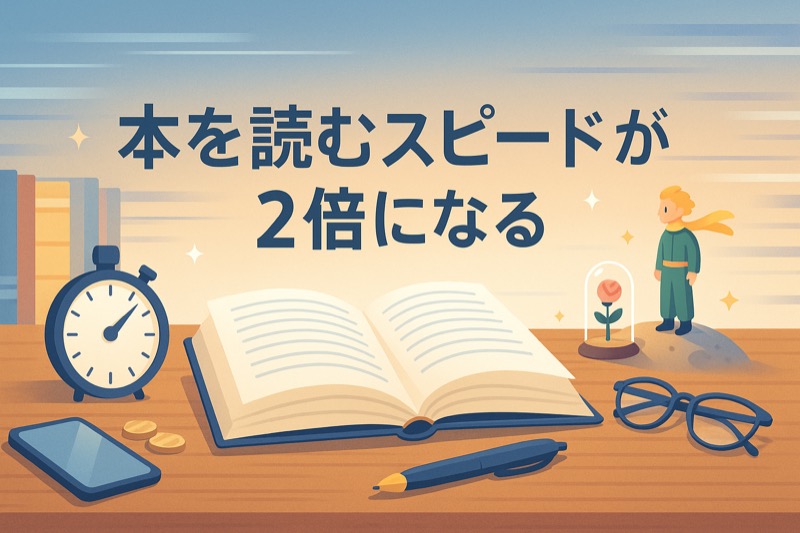
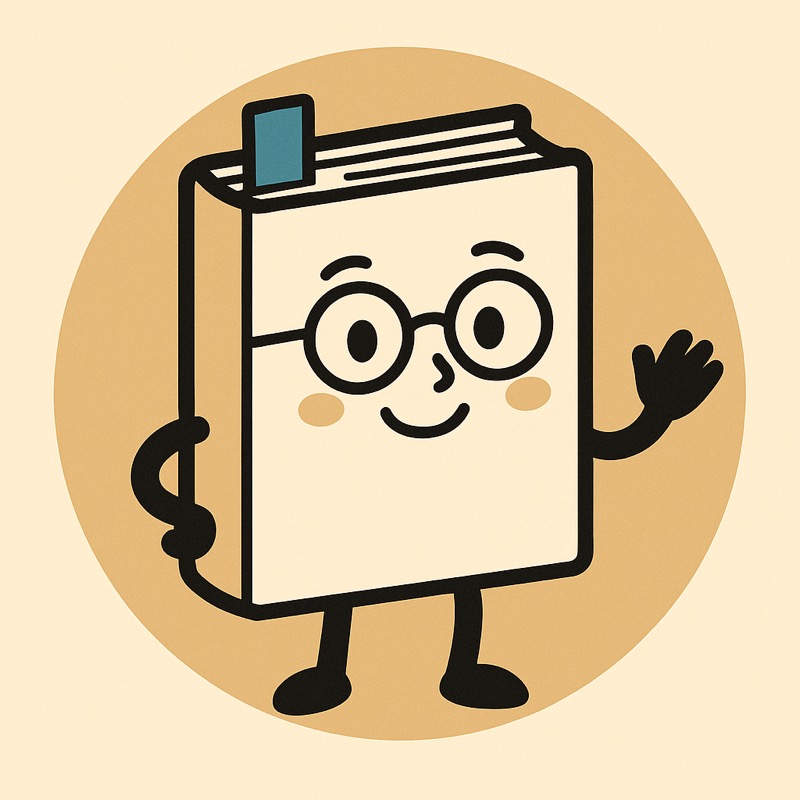
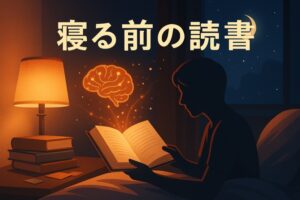
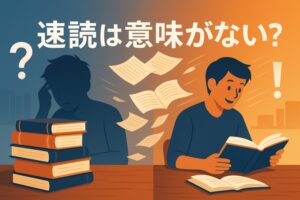
コメント