「読書感想文なんて、正直めんどくさい…」
高校生なら一度はそう思ったことがあるのでは?
忙しいし、本を読む時間も気力もない。そんな時、ネットやAIに頼って“コピペ”で感想文をすませたくなる気持ち、痛いほどわかります。
でも実際、コピペってバレるの? みんなどんな方法を使ってるの? 先生にはどう思われるの?
この記事では、高校生がやりがちな読書感想文のズル4パターンと、そのリスクやバレる可能性、AIの使い方や回避方法まで、リアルに解説します。
読書感想文に悩んでいる人が、無理せず・ズルせず・でもラクに書く方法を見つけられるはず。
「もう書けない…」と投げ出す前に、まずはこの記事を読んでみてください。
「読書感想文、正直めんどくさい…」その気持ち、めっちゃわかる
「読書感想文、書きたくない。」
そう思ってこのページにたどり着いたあなたの気持ち、めちゃくちゃわかります。
だって、そもそも読書感想文って“読書”も“作文”も両方めんどくさい。しかもそれを「ちゃんとやれ」とか「心を込めて書け」とか、先生は簡単に言うけど、こっちはそんな余裕も感情も残ってないんですよ。
📝 高校生の本音:
・部活でクタクタ。
・バイトで疲れてる。
・スマホの通知が気になって本なんか開けない。
・感想なんて「特になし」です…。
それなのに「800文字以上で、構成も考えて、締切までに提出ね」って。
いや、こっちは読んでないし、書けるわけないだろ。
──そんなあなたが「とりあえず、読書感想文 コピペ」で検索した気持ち、痛いほどわかります。
本を読む時間もないし、読む気にもならない
読書感想文の最大の敵、それは「本を読む気力がない」こと。
授業に部活に課題に人間関係、毎日疲れてて、じっくり本を読むなんてそんな余裕あるわけがない。
そもそも、「自分のために本を読む」っていう経験、ほとんどないのが現実じゃないですか?
どうせ提出するだけだから、中身なんてどうでもいい
正直、「読書感想文なんてどうせ先生しか読まないし」
「評価もテキトーだし、ちゃんと読んでも読まなくても点数変わらんし」って思ってませんか?
それ、半分正解。でも半分は損してるかもしれません。
💬 実際には…
提出された読書感想文の「雑さ」や「誠実さ」は、意外と先生には伝わっています。
特に3年生で推薦や内申が絡む時期なら、読書感想文も“内申点の材料”になってること、知ってました?
「バレなきゃいい」からコピペで済ませたい
「だったらもう、ネットでそれっぽい感想文を探してコピペで済ませよう」
この選択肢、ぶっちゃけ、9割の高校生が一度は考えたことあるんじゃないでしょうか。
・過去に書いたやつを再利用する
・友達や兄弟に書いてもらう
・ネットに落ちてる感想文をコピペする
・AIに書かせてそのまま提出する
でも、それ、本当に“バレない”って思ってますか?
このあと、なぜ先生にバレるのか、そのリアルな理由をしっかり解説します。
読書感想文に正解がないからこそ逆に書けない
感想文がしんどい最大の理由、それは「正解がわからない」こと。
数学なら答えがあるし、英語なら文法がある。でも感想文には答えもルールもない。だからこそ、何を書けばいいかわからず、書き出せない。
「“感想”って何?」「面白いって書くだけじゃダメなの?」
そんな疑問を抱えたまま、苦しんでる高校生が多すぎます。
でも実は、ちょっと書き方を知るだけでラクになる
でも実は、読書感想文って“コツ”さえ知れば、そこまで難しくないんです。
テンプレートを使えば、読まずに書く方法もあります。AIだって「丸写し」じゃなく「補助ツール」としてなら使えます。
✅ この記事を読めばわかること:
・高校生が実際にやってるコピペの種類
・先生にバレる理由とタイミング
・ズルせず“ラクして書く”方法
・読書感想文を時短で終わらせるコツ
読書感想文がめんどくさいのは当たり前。でも、少しだけ知識を持って取り組めば、意外とサクッと終わります。
この先の章で、あなただけの“最短ルート”を紹介していきます。
高校生がやりがちな読書感想文コピペ4パターンを整理してみた
「読書感想文 コピペ」で検索しているあなた。
安心してください。ズルしたくなるのは、あなただけじゃないです。
ここでは、高校生が実際によくやっている“4つのコピペパターン”を整理して、それぞれの特徴やリスクについて解説します。
📌 注意:
「バレなきゃOK」と思っていても、先生は想像以上にコピペを見抜いています。
それぞれの方法の“落とし穴”もしっかり知っておきましょう。
① 自分が過去に書いた感想文を再利用する
一番バレにくいと思われがちなのが“過去の自分の文章をそのまま再提出する”パターン。
たとえば中学生のときに書いた感想文を、ちょっと直して高校で提出する……というようなケースです。
確かに、自分の書いたものなので“著作権違反”にはなりません。
でも、先生は「この子が今感じたことじゃないな」と案外気づきます。
- 文章の語彙が今と不自然に違う
- 年齢や学年がズレている内容になっている
- 同じ先生に前も提出していた場合は完全アウト
💡 ちょっと書き換えるくらいじゃ、バレます。
再利用するなら、感想の視点だけでも今の自分の考えにアップデートする必要あり。
② 友達や家族の文章をコピペする
意外と多いのが、「友達に見せてもらったやつをそのまま使う」というやり方。
また、兄弟や親が書いた感想文をもらってそのまま提出、というパターンもよくあります。
でもこれ、かなりリスクが高いです。
なぜなら同じ文章が複数人から出される可能性があり、先生の信頼を一発で失うからです。
- 友達と提出日が同じ場合、比較されてバレやすい
- 同じ表現・語尾・構成だと、すぐに違和感を持たれる
仲がいい友達ほど、使い回しには要注意。
「お互いバレたらどうする?」というリスク共有が必要になる時点で、割に合わないズルかもしれません。
③ ネット検索で拾った感想文を使う
最も王道なのが、「読書感想文 本のタイトル 感想文」と検索して出てきた文章をコピペする方法。
無料サイト・ブログ・掲示板など、探せば山ほど出てきますよね。
ただし、これはほぼ確実にバレます。
なぜなら先生たちも同じキーワードで検索してチェックしているからです。
⚠️ Google検索で見つかる文章=他の生徒も使ってる
→ 同じ文をコピペしている生徒が他にもいたら、即アウト。
たとえ構成を変えても、「それ、パクリだよね?」と疑われるレベルのテンプレ感が出るので要注意です。
④ ChatGPTやAIに書かせてコピペする
近年急増しているのが、ChatGPTなどのAIに読書感想文を書かせ、それをそのまま提出するというパターン。
一見「これ最強では?」と思えますが、実はここにも落とし穴があります。
- AIの文体は独特で、不自然に整いすぎている
- 同じキーワードで生成された文章は似たものが出回りやすい
- 先生がAI感知ツールを使って検出するケースも増えている
さらにAIには「読んだ実感」や「自分らしさ」がありません。
そのため、読んだ本と感想の内容がちぐはぐになってバレることもあります。
🤖 AIは補助としてなら有効。
自分の感想の下書きを作る、文章を整える用途に使うならアリ。
でも“丸写し”は、バレる確率が意外と高いので注意。
バレる?バレない?読書感想文のコピペが見抜かれる理由
「読書感想文をコピペして提出したら、先生にバレるのかな?」
そう思って不安になりながらも、「たぶんバレないでしょ」と軽く考えていませんか?
でも現実はそんなに甘くない。
高校での読書感想文のコピペは、想像以上にバレやすいです。
ここでは、先生が“違和感”から読み取るコピペの兆候や、バレる典型的な理由を3つに分けて紹介します。
⚠️ 結論:
コピペはバレます。特に「誰かと同じ文」「ネットにある文」「AIそのまま」はかなり危険です。
先生は“なんとなく違和感”で見抜いてくる
読書感想文のコピペで一番厄介なのが、「明確な証拠がなくても、先生が違和感で気づいてくる」という点です。
先生は毎年何十人、何百人分の感想文を読んでいます。その中で、あなたの“文体の不自然さ”や“語彙のズレ”はすぐに目に留まります。
- 普段の提出物と文体がまったく違う
- 使わないような難しい言葉が多すぎる
- 妙に整っていて“きれいすぎる”文章
💡 先生の「この子らしくないな」は最強のセンサー。
たとえ証拠がなくても、「呼び出し対象」になる可能性は十分あります。
クラス内で文章がかぶっていると即アウト
友達と同じサイトから読書感想文をコピペしたり、兄弟で同じ文章を流用したり…。
似たような内容が複数提出された場合、先生は一発で気づきます。
| バレやすいシチュエーション | 理由 |
|---|---|
| 同じクラスで同じ本を選んだ人が多い | 同じようなフレーズ・感想が並ぶ |
| 兄弟姉妹で同じ学校に通っている | 過去提出物と照らし合わせられる |
「バレないだろう」と軽い気持ちでやったコピペが、同時に出された誰かのせいで共倒れになることもあります。
AI文章やテンプレは表現でバレやすい
ChatGPTなどのAIを使った感想文作成も増えていますが、AIが書いた文章には「クセ」があります。
それが、読書をしていない人が書いたことを“におわせてしまう”原因になります。
- 「~と感じました」「~のように思いました」が多すぎる
- 誰にでも当てはまる曖昧な表現ばかり
- 登場人物や内容に触れていない“フワッとした感想”
🤖 先生はAIのクセにも敏感。
文章がキレイすぎる、抽象的すぎる、構成が完璧すぎる…これ全部「AIくさい」と思われる要素です。
AIを使うこと自体が悪いわけではありませんが、そのままコピペ提出は非常に危険です。
自分の言葉を加える、表現を変えるなどの工夫をしなければ、見抜かれてしまう可能性が高くなります。
コピペで読書感想文を書くメリット・デメリットを正直に語る
「コピペで読書感想文って、正直ラクじゃん?」
そう思ってる高校生、多いはずです。
実際、ネットやAIを使えば、今や感想文なんて数分で完成する時代。でも…そのコピペ、ほんとに“得”してますか?
ここでは、高校生が読書感想文をコピペで済ませることのメリットと、意外と重たいデメリットを包み隠さず正直に語ります。
📌 この記事の結論:
短期的にはラクでも、長期的に見ると損してる可能性が高いです。
「ズルくない時短法」もあるので、それも後半で紹介します。
【メリット】とにかく時短できてラク
やっぱり最大のメリットは、時間と手間を大幅にカットできること。
本を読まずに、検索 or AIで出てきた文章をコピペすれば、数分で読書感想文が完成。
忙しい高校生活の中で、これは確かに魅力的。
- 部活やバイトで忙しい人にはありがたい
- 読書が苦手でも“とりあえず提出”はできる
- 時間を他の教科や趣味にまわせる
✅ コピペの「効率性」は事実。
特に「提出すること」が目的なら、最速で終わらせられる手段ではあります。
【デメリット】バレたときのダメージがデカい
でも当然ながら、バレたときのリスクはかなり大きいです。
先生に「コピペだ」と判断された場合、内申点・信頼・推薦など、全部に悪影響が出る可能性も。
| バレた時の影響 | 詳細 |
|---|---|
| 先生からの信頼が下がる | 次の提出物や評価にも響く |
| 内申点に影響する | 高校3年生なら推薦にも直結 |
| 謝罪や再提出を求められる | 結局あとで手間が増える |
⚠️ 「バレなきゃOK」は通用しない。
最近はAI感知ツールやコピペチェックも導入されていて、先生も甘くありません。
【デメリット】評価されないし自分のためにならない
もう一つ見落としがちなのが、せっかくの課題なのに「評価対象にならない」こと。
読書感想文って、先生にとっては「あなたの考え方」や「言葉の使い方」を知るチャンスなんです。
でも、コピペされた文章では、あなたの内面は1ミリも伝わらない。つまり、「この子は何も考えてないな」と思われて終わりです。
- 作文スキルも語彙力も上がらない
- 思考力・表現力のトレーニングにならない
- 将来、書く力が必要なときに困る
💬 “ズルして乗り切った感”はあっても、「やってよかった」とは思えない。
それがコピペ最大のデメリットです。
それでも感想文が書けない高校生へ|“ズルしない時短術”あります
「バレるのは怖い、でも読む時間もないし、書ける気がしない…」
そんな高校生へ、“コピペせず、ちゃんと書ける時短テク”を紹介します。
読書感想文って、「読まずに書く=ズル」じゃなく、「要点を押さえて書く=時短」という方法もあるんです。
✅ この記事では…
・本を全部読まなくても書ける本の選び方
・“読む代わり”に情報を得る工夫
・自分の言葉でサクッと書ける感想文の素材づくり
この3つを中心に、ズルしないけど手抜きできる方法を教えます。
読まずに書くための「本の選び方」
本を読むのが苦手な人こそ、「読まなくてもなんとなく内容がわかる本」を選ぶのが大事です。
つまり、情報が外にあふれていて、要点を拾いやすい本を選ぶことがコツです。
- 映像化された本(映画・アニメ・ドラマになっている)
- ベストセラーや話題になった本(レビューが豊富)
- 薄くて短時間で読める本(100〜150ページ程度)
特におすすめなのは映画化された本。あらすじ・登場人物・感想が動画でも手に入るので、実際に読んでなくても“読んだふう”の感想文が書きやすいです。
目次・帯・レビューを使って要点をつかむ方法
本を全部読まなくても、「外から得られる情報」を活用すれば、感想文に必要な要素はだいたい揃います。
以下の3つを活用して、内容を“つかんだふう”にしましょう。
| 使える情報 | ポイント |
|---|---|
| 目次 | 本の構成・テーマが分かる。「何について書かれているか」を把握できる。 |
| 帯・裏表紙 | 本の魅力・要約・キャッチコピーが書かれている。感想文の導入に使える。 |
| Amazonや書評サイトのレビュー | 他の人の感想から、自分の“感想っぽいこと”が見つかる。 |
💡 コツ:
レビューは「自分と似た考え」を探すために使う。
まる写しじゃなく、「こう感じた人もいたんだ」と参考にするのがポイント。
3行日記で素材をストックする読書ノート活用術
いざ感想文を書こうとすると、「何を書いていいかわからない」と詰まってしまう人も多いはず。
そんなとき役立つのが、読んだページ数に関係なく思ったことを“3行だけ”書いておく読書ノートです。
やり方は超シンプル:
- 読んだ/見た/調べた本のタイトルを書いておく
- 「気になったところ」や「へぇと思った部分」を3行だけメモ
- 書いた日付と気分も添えておくと、あとで使いやすい
📓 この3行ノートが、感想文を書くときの“ネタ帳”になります。
本の感想=内容の要約じゃなくて、「自分が感じたこと」でOK。
読書ノートにそのヒントが残っていれば、スラスラ書けるようになります。
「書けない」のは、ゼロから文章を考えようとするから。
素材を集めておくだけで、読書感想文の“スタート地点”がぐっとラクになりますよ。
AIで読書感想文を作るのってどうなの?活用方法と注意点を解説
「ChatGPTとかBardに感想文を書いてもらえばよくない?」
今どきの高校生なら、一度は考えたことがあるはず。
実際、「AI 読書感想文 コピペ」で検索すれば、出てくる出てくる…AIが書いたそれっぽい文章がゴロゴロ。
でもちょっと待って。“そのまま提出”してしまうのは、かなり危険です。
ここでは、AIをうまく活用する方法と、絶対にやっちゃダメな注意点を解説します。
⚠️ 結論から言うと:
AIを「道具」として使うのはアリ。でも「答え」としてコピペするのはアウトです。
AIを「使う」のと「丸写しする」のは違う
AIは確かに便利。タイトルやあらすじを入れれば、数秒で読書感想文らしき文章を出力してくれます。
でも、それをそのまま提出するのは、「自分の感想」ではないし、バレたときのリスクも大きい。
| AIを使う=〇 | AIをコピペ=× |
|---|---|
| 文章構成のヒントを得る | AIが書いた文章をそのまま提出 |
| 自分の感想を整理するために使う | 内容を読まずにAI任せ |
| 語尾・言い回しのチェック | 自分の言葉を一切入れない |
✅ 「道具として使う」ならAIは強力な味方。
でも「考えずに丸写し」は、自分の信用を落とすだけです。
AIの文章は自然だけど、あなたらしさはゼロ
AIが書く文章は文法的に正しくて、読みやすい。
でも逆に言えば、誰が書いても同じような“無難すぎる感想”になりがちなんです。
- どの感想文も「主人公の成長に感動しました」で終わる
- 読んでないのに「感情移入できました」と書いてある
- 作品の内容に具体的に触れていない
こうした文章は、先生の目には「中身が空っぽ」に映ります。
「この子はちゃんと読んでないな」と、すぐに違和感を持たれる原因になります。
💬 感想文に必要なのは、「あなたらしさ」
AIにはそれがありません。だからこそ、少しだけでも自分の視点を入れることが大事なんです。
AIを使っても「読んだフリ」になる文章は避けるべし
そもそも読書感想文とは、「本を読んだあとにどう感じたかを書く」もの。
つまり「本を読んだ」という前提がないと、内容がちぐはぐになるんです。
AIが出してくれる文章を見て、「これでいける!」と思っても、
・登場人物の名前を間違えてる
・ストーリーの流れに矛盾がある
・感想と内容が一致していない
こういう“読んだフリ”が透けて見える内容だと、すぐにバレます。
⚠️ AIは「読書感想文メーカー」ではない。
あくまで補助ツール。
「本当に読んだうえで、自分で感じたこと」を書かないと、感想文にはなりません。
AIは便利だけど、使い方を間違えると逆効果。
「考えないための道具」ではなく、「考えるきっかけ」に使うのが正解です。
読書感想文に使える!高校生向け“書きやすい本”3選【2025年版】
「どの本を読めば感想文が書きやすいのか分からない…」
そんな高校生のために、2025年の読書感想文にぴったりな“書きやすい本”を3冊厳選しました。
「できれば本は読みたくない」「コピペは怖いけどラクしたい」そんな人にこそおすすめのラインナップです。
✅ 選定基準:
・短時間で読める(200ページ以内)
・レビューが多く、感想の参考になる
・読書感想文で“自分の言葉”が書きやすい
1冊目:短くて内容が共感できるエッセイ系
『嫌われる勇気』(岸見一郎・古賀史健)
アドラー心理学をベースに、「自分はこのままでいいんだ」と思わせてくれる対話形式のエッセイです。
会話ベースなので読みやすく、読書が苦手な高校生でもスラスラ読めるのが魅力。
- 読書感想文で書きやすいテーマ:自己肯定感/人間関係の悩み/将来の不安
- ポイント:自分の経験と結びつけて書けば“自分の言葉”になる
📘 読んでなくてもレビューが豊富!
Amazonや書評サイトで感想がたくさん載ってるので、コピペせず“参考”にしやすい1冊。
2冊目:映像化されていて話の流れをつかみやすい本
『君の膵臓をたべたい』(住野よる)
映画・アニメ・マンガなど多数メディア展開されており、内容を事前に知っていれば“読まずに書ける”感想文の王道本とも言えます。
- 読書感想文で書きやすいテーマ:命/友情/人とのつながり
- おすすめ理由:あらすじが動画サイトでも解説されていて、話の流れをすぐ把握できる
🎬 映像作品を見てからでもOK!
“ズルしない”感想文に仕上げるには、自分が感じたことを1つ入れるだけでOK。
3冊目:高校生の悩みに寄り添ったテーマの本
『ハケンアニメ!』(辻村深月)
“好きなものを仕事にするって、どういうこと?”
将来や夢に迷う高校生に響くテーマで、就職や進学、夢に悩んでいる人が感想文にしやすい1冊です。
- 読書感想文で書きやすいテーマ:進路/努力/夢と現実
- 内容が“自分ごと”として共感しやすい
💬 この本のいいところ:
「自分のことみたいだった」と書くだけで、立派な感想文になるのがポイント。
結論|コピペを卒業して、「自分の言葉」で書くとめっちゃスッキリする
ここまで読んでくれてありがとう。
「コピペしたいけど、バレたくない」
「AIに任せたいけど、それって大丈夫?」
そんな悩みや迷いを抱えていた高校生のあなたへ、最後に一番伝えたいことがあります。
🎯 コピペより、自分の言葉で書くほうが、結果的に“ラク”で気持ちいい。
ズルせず、でも完璧を求めずに「それなりでいいや」と書く。
そのスタンスが、いちばんスッキリ終われる感想文になります。
読書感想文は、自分と向き合ういいきっかけになる
読書感想文って、ただの課題じゃありません。
本を通して「自分がどう感じたか」を初めて意識できるチャンスなんです。
面白かった、つまらなかった、主人公にイラついた。
どんな感情もOK。それが“あなたの言葉”だから。
学校の課題として書く読書感想文が、実は自分の気持ちや考え方を整理する入口になることもあります。
ちょっとの工夫で“ズル”よりずっとラクに書ける
ズル(=コピペ)って、「何も考えずに終わる」のはラクだけど、「バレたら怖い」ってストレスもあるんですよね。
それなら、レビュー・帯・目次・AIのヒントをちょっと使って、自分の言葉でサクッと書いた方が気がラクです。
- 本を全部読まなくても、要点を拾えば書ける
- 書き方の型(テンプレ)を使えば、迷わない
- 最初の1文さえ出せれば、意外と書ける
✅ 「書けない」じゃなくて、「書き方を知らなかった」だけ。
1回でも「自分の言葉で書けた!」を体験すれば、次からはもうコピペに戻れません。
自分の言葉で書いた文章は、読み返しても気持ちいい
不思議なもので、たとえ下手でも、自分で書いた文章は“納得感”があるんです。
書いてるときはめんどくさかったのに、後から読み返すと「俺、けっこういいこと書いてるじゃん」って思えたりする。
逆に、コピペした感想文は提出したあと、なんとなく後ろめたさや不安が残ります。
そして提出してからも「バレたらどうしよう」って気になり続ける…。
📚 自分で書いた感想文は、提出しても“後悔がない”。
評価がどうであれ、「これが自分の言葉だ」って思えることが、一番大事。
だからこそ、読書感想文は“うまく書く”より“自分で書く”ほうが100倍価値があるって、最後に伝えたい。
まとめ|読書感想文、ズルしないほうが結果的にラクになる
「高校 読書感想文 コピペ」と検索してこの記事にたどり着いたあなた。
正直に言えば、今のあなたは「なんとか楽して終わらせたい」「とりあえず出せればいい」と思っているかもしれません。
その気持ち、ほんとによく分かります。部活にバイトに課題に忙しい中、感想文なんて優先順位は最下位ですよね。
でも、この記事で伝えたかったのは「コピペ=悪」じゃなく、「自分の言葉で書くほうが、実は早く終わる」という事実です。
コピペには確かに“時短”のメリットがあるかもしれません。
でも、バレたときのリスクや、提出後に残る後ろめたさ、内申や推薦への影響を考えたら…ほんの数十分、自分で書いた方が圧倒的に気持ちよく終われます。
✅ まとめポイント:
・コピペはバレる時代、特にAI文章はすぐ分かる
・「書けない」のは才能じゃなく、“やり方”を知らないだけ
・読まずに書ける本や時短テクを使えば、ズルしなくても感想文は終わる
・自分の言葉で書くと、想像以上にスッキリする
今やAIやネットに頼ることは当たり前。でも、**全部任せっきりじゃなく、「ヒントとして使う」くらいがちょうどいい。**
読書感想文は、うまく書かなくていい。完璧じゃなくていい。
「読んでこう思った」それだけでも、立派な“自分の言葉”です。
結局のところ、読書感想文は作文でもなく、評論でもありません。
あなたの気持ちを、あなたのペースで言葉にするだけでいいんです。
コピペでビクビクしながら出すより、多少雑でも「これは自分の文章だ」って思える方が、きっと気持ちいい。
最後にもう一度だけ。
ズルしないで書く方法、ちゃんとあります。しかもそんなに難しくない。
「とりあえず1文書いてみようかな」と思えたら、それがもう前進です。
この記事をきっかけに、あなたの読書感想文が“自分の言葉”で仕上がることを願っています。
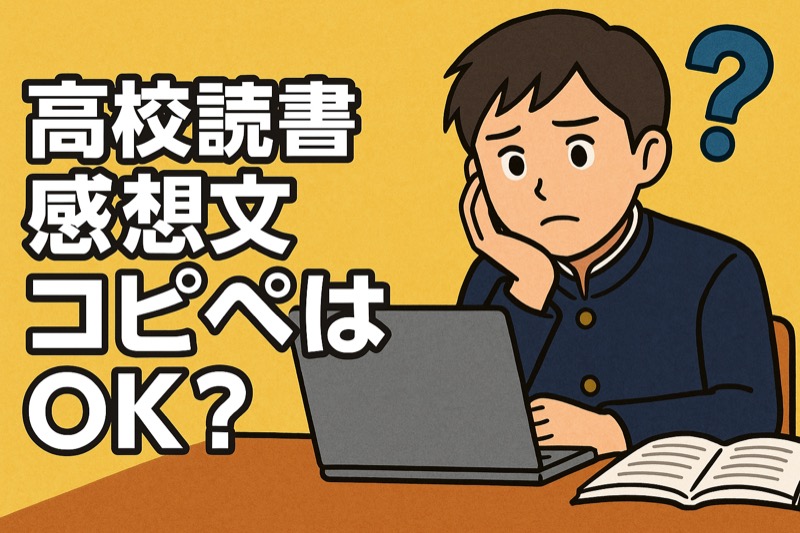
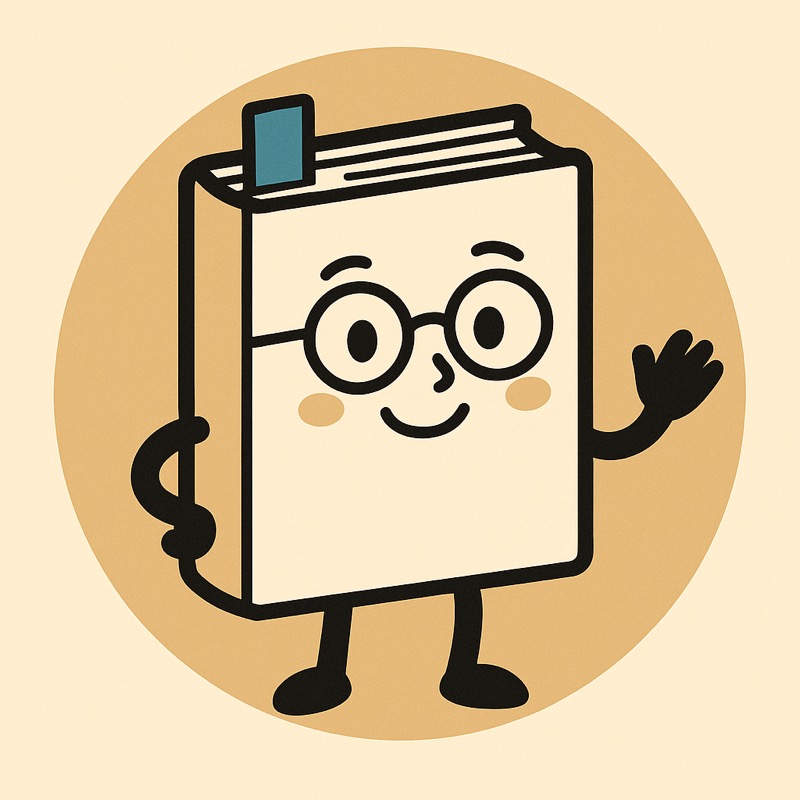
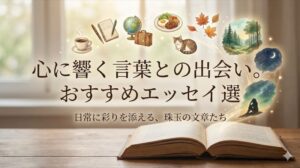


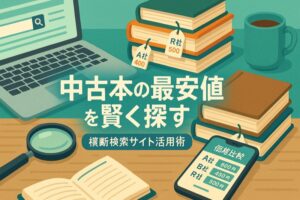


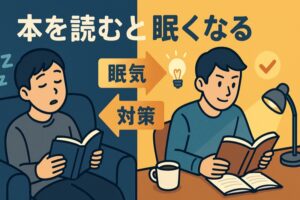

コメント